ヨーロッパ・イベリア半島の東側に位置するスペインでは、ハゲワシが多く生息しています。
ところが、隣接する西側のポルトガルでは、その数はごくわずかです。
両国の国境は陸続きで、ハゲワシは何百キロも自由に飛ぶことができます。それなのになぜポルトガルにはハゲワシがほとんどいないのでしょうか。
これは、地形が単に物理的な障壁になっているという話ではありません。
本記事はハゲワシが国境を越えることができない理由について解説しています。
この記事の要約
- スペインにはハゲワシが多いが、隣のポルトガルにはほとんどいない
- 理由は餌の違い:スペインは家畜の死体を野外に置けるが、ポルトガルは法律で禁止している
- 餌が豊富なスペインに留まり餌が少ないポルトガルには行かないため、政策の違いが国境を「見えない壁」にしている
スペインに生息するハゲワシ

ハゲワシはタカ目タカ科に属する猛禽類のうち、主に腐肉を食べる大型の鳥の総称です。
スペインにはシロエリハゲワシやクロハゲワシなどのハゲワシ類が多く生息しています。
シロエリハゲワシはヨーロッパ、アジア、北アフリカに広く分布する大型のハゲワシで、体長は約93~122cm、翼を広げたときの長さは約2.3~2.8m、オスもメスもおおむね6~10kg程度です。
白い頭部と首、黄色いくちばし、暗色の翼を持ちます。
一方、クロハゲワシはユーラシアに広く分布する大型のハゲワシで、体長は約98~120cm、翼を広げたときの長さは約2.5~3.1メートル、体重は6~14kgあり、現存するハゲワシの中でも最大級の鳥のひとつです。
全身は黒褐色で、頭部は淡い灰色の産毛に覆われ、巨大なくちばしと幅広い翼を持ちます。
クロハゲワシは非常に高い高度まで飛ぶことができ、実際にエベレストの標高6,970メートル付近で観察された記録もあります。
この能力は、空気が薄い高い場所でも酸素をしっかり取り込める、特別なヘモグロビンのおかげで成り立っています。
また、日本には生息していませんが、迷鳥として北海道から沖縄まで各地で記録があります。
このように、飛翔能力の高いハゲワシがなぜ国境を越えてポルトガルに行こうとしないのでしょうか。
国境を越えないハゲワシ

実際に、スペインのシロエリハゲワシ60羽とクロハゲワシ11羽を対象にGPS追跡調査を行ったところ、約2年間の間でポルトガル側に国境を越えたハゲワシはわずか6羽で、全体の4.4%にとどまりました。
このことから、国境を越えた地点でのハゲワシの位置情報は急激に減少していることがわかります。
当然のことながら、ポルトガルにおけるハゲワシの個体数は少なく、現地個体群は絶滅の危機に瀕しています。
スペインとポルトガルの国境付近の地形は、主に河川の谷によって形成されており、気候や地形、土地被覆において国境をまたいで急激な変化は見られません。
そのため、国境自体がシロエリハゲワシやクロハゲワシの移動に影響を与える物理的な障壁となっているわけではないと考えられます。
これはまるで見えない壁が存在しているようです。
ハゲワシが国境を越えない理由

実はこの違いの背景には、家畜の死骸をめぐる餌資源の差が深く関係しています。
野外に放置される家畜の死体の量が地域によって異なることが、ハゲワシの分布に影響を与えている可能性が高いのです。
ヨーロッパの一部地域では、死んだ家畜を山中や草原などに放置し、ハゲワシやキツネなどの野生動物が自然に処理するという形が一般的でした。
しかし、2001年、欧州連合(EU)は牛海綿状脳症(BSE)危機を受けて、家畜の死体を野外に放置することを禁止する規制を導入したのです。
BSEは牛に発生する伝達性海綿状脳症の一種で、俗に「狂牛病」とも呼ばれます。脳や脊髄に異常なプリオンというタンパク質が蓄積することで、牛は神経症状を示し、最終的に死に至ります。
この感染は、異常プリオンが混入した肉骨粉入りの飼料を牛が食べることで広がったことが確認されています。
BSEは1990年代後半から2000年代初頭にかけて世界的に注目され、特にイギリスでは大規模な感染が報告されました。
BSEに感染した牛肉を通じて人に感染する、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病のリスクも指摘され、食の安全性が大きく問題視されました。
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病が発症すると、記憶障害や行動の異常、歩行障害や筋肉のこわばりなどの神経症状が急速に現れ、進行すると命に関わります。
ただし、現在では、牛肉の安全管理が徹底されているため、感染例は非常にまれです。
このように、EUでは感染症を広げないために、家畜の死体を完全に管理・処理する目的で野外に放置することを禁止したのです。
しかし、この措置によって、シロエリハゲワシやクロハゲワシが利用していた家畜死体という食料源が急激に減少しました。
その結果、腐肉を食べる動物たちのコミュニティー構造が変わったり、生態系の中での動物同士の関係が乱れたりしたのです。
さらに、死んだ家畜を人間が運んで処理するようになったことで、CO2の排出量が増えるなど、さまざまな生態学的影響が生じています。
ハゲワシは死んだ動物の肉を主に摂食する腐肉食者として、生態系において清掃員の役割を果たしています。
彼らは動物の死骸を効率的に処理することで、病原菌や寄生虫の拡散を防ぎ、環境の衛生を維持します。
また、死肉を消費することで、他の動物との食物競争や生態系内の栄養循環にも寄与しています。
例えば、死骸の分解によって土壌に栄養が還元され、植物の成長を助ける効果もあります。
さらに、ハゲワシがいることで、他の死肉を食べる動物たちの食べ方や行動にも影響を与えます。
群れで効率よく死骸を分け合うことができるようになったり、異なる種類の動物同士がうまく共存できるようになったりしているのです。
このため、のちに科学者や保全管理者の合意により、EUは一部の規制を見直し、衛生面での要求と生物多様性保全の両立がある程度可能となりました。
ただし、新しい法律では各加盟国に義務的な統一規則は設けられず、各国が独自の家畜死体処理ルールを作ることが認められたのです。
この結果、イベリア半島では隣接する国同士で大きく異なる運用が行われることになっています。
スペインではシロエリハゲワシやクロハゲワシへの餌やりを目的とした死体の処理が柔軟化され、事実上の死体放置禁止の制限は緩和されました。
また、のちの欧州規制では、スカベンジャーのための餌場保護区域が設定され、食料不足や関連する環境負荷の緩和が図られています。
一方、ポルトガルでは政府が依然として家畜死体の野外放置を原則禁止しており、許可された限られた餌場にのみ厳格な条件のもとで供給が認められるという状況が続いています。
この政策の違いが、スペインとポルトガルでのシロエリハゲワシやクロハゲワシの生息・採餌行動に大きな影響を与え、国境が事実上の生態学的障壁となる原因となったのです。
まとめ

今回の研究結果から、政策の違いが動物の生態に直接影響していることが示されました。
研究では、政策立案者や保全管理者に対し、衛生管理と生物多様性保全の政策を統合し、国境を越えた協力を強化することが望ましいとされています。
また、科学的データに基づき、動物の行動や食料の状況を考慮して政策を設計することが、生態系の機能を守り、種の保全を確実にするうえで重要であると示唆されています。
関連記事:おすすめ鳥の図鑑19冊を徹底レビュー | ジオチャン
ハゲワシをもっと知りたい方へ
ハゲワシの生態やたくましい姿にご興味を持たれた方には、「ハゲワシ:フォトブック」がおすすめです。
本書は、荒涼とした風景で生きるハゲワシの姿を美しい写真で綴った一冊です。
言葉を使わずに読者をハゲワシの世界へと誘い、荒野を飛び回る姿や獲物を捕食する様子、仲間との交流など、その生態や生活の一端が見事に描かれています。
ハゲワシが生息する地域の風景や、その環境に適応するための様々な工夫も写真に収められており、自然の中で生きる鳥たちの姿や生態に興味を持つ方や、野鳥観察を楽しむ方にとって魅力的な内容となっています。
豪華な装丁と高品質な印刷により、美しい写真が一層際立つこのフォトブックで、ハゲワシの厳しい生存環境や美しい姿に触れてみてはいかがでしょうか。
この記事は動画でも見ることができます。


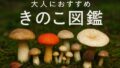

コメント