世界最大の陸生甲殻類として知られるヤシガニは、太平洋の島々では高級食材として扱われ、沖縄でも伝統的に食用とされてきました。
ただ、ヤシガニは食べたものによっては毒を蓄えることがあるため、経験的な知識で安全に扱う必要があります。さらに乱獲で数が減り、今では保護対象にもなっています。
それなら、養殖すれば安全で持続可能なヤシガニを食べることができるのでは、と思う人もいるでしょう。
実は研究者たちもこれまでにヤシガニの養殖を挑戦してきたのですが、そこにはいくつかの壁がありました。
本記事はヤシガニが養殖できない理由について解説しています。
この記事の要約
- ヤシガニは成体になるまで6年以上かかり、長期的な管理が必要
- 幼生期を海で過ごす複雑なライフサイクルで、海水温や餌の条件に非常に敏感
- 脱皮に必要な適切な湿度や巣穴環境の再現が困難で、脱皮不全や共食いが発生する
ヤシガニ食の伝統

ヤシガニは主にグアムなど西太平洋の島々で伝統的に食べられてきました。
特にグアムのチャモロ族は、ヤシガニを結婚式などの儀式や祝祭で提供する文化を持ち、何世代にもわたり食材として親しんできました。
その肉はロブスターのように柔らかく、地域の伝統的な料理として重宝されています。
日本でも、かつての宮古島や沖縄本島では地域の食文化の一部として親しまれてきました。
その濃厚な味わいから高級食材として珍重され、家庭や地域の特別な料理として食べられてきたのです。
ヤシガニの毒性について

ヤシガニ自体はもともと毒を持つ生物ではありません。
しかし、ミフクラギの果実など、特定の植物の果実を食べると、その中に含まれる心臓に作用する強力なステロイド系配糖体がヤシガニの体内、特に肉に蓄積されます。
そのため、人がこうしたヤシガニの肉を食べると、果実を直接食べた場合と同様の毒性を示すことがあります。
ヤシガニの中毒例は実際の症例報告で明らかになっています。
人が毒を蓄えたヤシガニの肉を食べると、まず嘔吐や下痢などの消化器症状が現れ、その後、心拍数の低下や低血圧を引き起こし、重篤な場合は心停止に至ることもあります。
網羅的な解析によれば、23例の中毒例のうち4例が死亡したと報告されています。
どの部位に毒が集中するかは研究でも一定しておらず、食用の肉部分全体に毒が存在し得るため、脚だけ食べれば安全という単純な判断は危険です。
実際の臨床報告でも、肉全体の摂取による中毒例が確認されています。
そのため、太平洋の島々では、長年の経験に基づいた伝統的な知識が安全対策として活用されてきました。
現地の人々は、ヤシガニがどの果実を食べていたかを観察し、ミフクラギなど毒性のある植物の近くで捕れた個体を避けるなどの方法で安全性を確保してきました。
科学的な検査が一般的でない時代には、この経験則が最も現実的な安全対策だったのです。
宮古島でも、同様に現地での経験則や知識に基づいてヤシガニを扱っています。
許可を得た飲食店では、仕入れる個体の出自や採取場所を確認し、ミフクラギの果実を食べていないと考えられる安全な個体だけを提供することで、食文化を守りつつリスクを最小限にしています。
ちなみに、毒を持ったヤシガニは茹でても赤くならないという迷信がありますが、赤く変色する個体が安全であるという科学的根拠はありません。
そのため、養殖環境で安全な餌だけを与えて育てれば、こうした毒のリスクはなくなるはずです。
個体数の減少について

また、近年では過剰な捕獲や生息地の開発、外来動物による卵や幼体の食害、道路や開発による交通事故などが重なり、世界的に個体数が減少しています。
ヤシガニはかつては食用や装飾用として細々と捕獲されてきました。しかし20世紀後半に観光客が増加すると、商品価値が高まり、乱獲が進むようになりました。
グアム島では観光客向けにヤシガニ料理が提供されるようになってから島内の個体が激減し、隣の島々から取り寄せるようになりましたが、それらの島々の個体も次第に減少しました。
1989年に行われた南太平洋4カ国の調査では、バヌアツの首都エフェテ島周辺の島々でヤシガニは乱獲により激減しており、ホテルや食堂で利用される大型オス個体は、北西部のトレス諸島から小型機で運ばれ、消費地へ供給されていたことが報告されています。
捕獲は主に1から2kgのオス個体に偏っており、メスや小型個体は体長制限で保護される一方、家庭用として少量利用されることもありました。
しかし、資源の多い島でも年間約25%の減少が見られ、2011年時点では辺鄙な島々の個体も減少していることが懸念されています。
このように、特に大型のオスだけを市場に出す大型オス選択利用により、優秀な遺伝子を持つ個体が不足し、繁殖力の弱体化や資源更新の遅れが起こる可能性があります。
そのため、ヤシガニはIUCNのレッドリストで絶滅危惧種に分類され、地域によっては厳しい保護措置が取られるようになっています。
沖縄でも乱獲や生息地の減少により、数が減少したため、現在では繁殖期を含む長期間の禁漁期間や、捕獲・販売に関する厳しい規制が敷かれています。
正式な許可を得たごく一部の店舗でしかヤシガニを提供できず、その希少性から価格は高騰しています。
ヤシガニのライフサイクル

このため、ヤシガニの保全や個体群の回復を目指して、人工的な繁殖や養殖技術の開発が重要視されてきました。しかし、ヤシガニの生活史を考えると、養殖が非常に難しいことが分かります。
まず、ヤシガニのメスは陸上で卵を抱えますが、卵の孵化には海水が不可欠なため、孵化の直前に海岸付近まで移動します。
こうして放出された幼生は、海洋の表層でプランクトンとともに漂いながら3から4週間を過ごします。この間に多くの幼生が捕食されます。
また、海水温や餌の条件にも非常に敏感で、人工環境での飼育は極めて難しいです。
そして、海中で3から5回のゾエア期を経てグラウコトエ幼生となります。
この過程は25から33日かかりますが、この段階でも生存率は低く、多くの幼生が死んでしまいます。
グラウコトエ幼生に達すると海底に定着し、適当な大きさの貝殻を見つけて身に着け、海岸線に移動します。
その後は海から離れ、水中で呼吸する能力を失い、成体へと成長していきます。
このように、ヤシガニに限らず、ズワイガニや毛ガニ、タラバガニ、さらにはイセエビなど、幼生期を海で過ごす多くの甲殻類は、人工環境で育てることが非常に難しいことが知られています。
関連記事:カニの養殖ができない理由とその試みについて | ジオチャン
ヤシガニ養殖の試み

そんな中、2005年に東京海洋大学は、幼生の生存率や発育期間に対する飼育温度の影響を明らかにすることを目的に研究を行いました。
研究には抱卵したメス個体を室温で飼育し、そこから孵化した第一期ゾエア幼生が実験に用いられています。
そして、幼生を6段階の恒温条件(18.9℃、21.3℃、24.6℃、27.0℃、29.8℃、32.4℃)で飼育し、生存率と発育の様子を調べました。
その結果、最も低い18.9℃では、第一期ゾエアから第二期ゾエアに脱皮できず、すべての幼生が53日で死亡しました。
21.3℃では、わずか1匹がメガロパ期まで生き残りましたが、生存率は依然として低いままでした。
しかし、24.6℃以上に温度を上げると、生存率が大幅に向上し、特に27.0℃と29.8℃ではメガロパ期までの生存率がそれぞれ85.6%と82.2%と非常に高くなりました。
また、温度が高くなるほど発育が早まることもわかりました。
このように、ヤシガニの幼生は温度に非常に敏感であり、最適温度であればメガロパ期まで順調に育成できることが明らかとなったのです。
この研究は人工的に幼生を育てるための条件を明確化し、将来的な資源回復や養殖技術開発の基盤となる重要な知見を提供しています。
また、北マリアナ諸島のロタ島では、2006年から2008年にかけて、廃棄食品を利用したヤシガニ幼体の飼育実験が行われました。
このプロジェクトでは、約7.6メートル四方、高さ約1.8メートルの飼育用囲いを設置し、体長約1.3センチの幼体を104匹収集しています。
そして、囲いには塩水池や淡水池、土壌、サンゴ石、枯れ木などが入れられ、自然環境に近い飼育空間が再現されました。
この時、幼体はココナッツを好んだほか、バナナ、パパイヤ、スイカ、サトウキビ、生肉なども摂取していたことがわかっています。
飼育の結果、年間0.5から2センチの成長が確認され、成熟には約6年かかることがわかりました。
この取り組みは、野生個体の保護と地域経済の活性化の両面に貢献する可能性を示しており、地元農家からの関心も高まっています。
しかし、このような地域レベルでの実験的な成功例はあるものの、養殖の一般化にはまだ至っていません。
ヤシガニは成体になるまで6年以上かかるため、完全養殖として持続させるには非常に長期的な管理が必要です。
また、1から2年に1度脱皮を行いますが、飼育下で脱皮に必要な条件を整えるのは非常に困難です。
脱皮には水分が必要で、砂の中で行うのが理想ですが、適切な湿度や深い巣穴環境を再現するのは難しく、脱皮不全や疾病が起きると幼体や成体が命を落とすことがあります。
沖縄の飼育場での経験でも、脱皮中に死亡したり共食いが起きることが報告されています。
このように、研究レベルでは幼生や幼体の育成は可能ですが、設備や餌、管理の手間やコストが非常に大きく、現時点では大量生産や商業利用に耐える安定性や効率性は確立されていません。
ヤシガニの保全活動について

これまで見てきたように、ヤシガニは過剰採取の影響で、特に大きなオス個体が減少し、性比がメスに偏る傾向にあります。
また、過去数十年にわたる採取の影響により、個体や集団の遺伝的多様性も低下している可能性があります。
そのため、人工環境での養殖で個体数を増やすよりも、まずは自然個体群を保全し、性比や体サイズ、遺伝的多様性を維持することが、ヤシガニの資源管理において非常に重要です。
こうした取り組みは地域全体に拡大されるべきです。
関連記事:すさみ町立エビとカニの水族館レポート【世界的にも珍しい甲殻類専門の水族館】 | ジオチャン
ナイトサファリで夜の生き物と出会う!ヤシガニ体験ツアー
石垣島ではナイトサファリツアーに参加すると、夜の森でヤシガニをはじめ、普段はなかなか見られない夜行性の生き物に出会えます。
道路や森の中をゆっくり歩くヤシガニのほか、オカヤドカリやミナミスナガニ、タイワンサソリモドキなど、驚きの生態を間近で観察できます。
ツアー中は現地のスタッフが丁寧に解説してくれるので、ゴイサギや巨大オオヒキガエルなどの珍しい生き物の行動も安全に観察可能。
6月下旬~7月の満月の夜には、オカガニの産卵を見られる特別なチャンスもあります。
興味がある方は、こちらのリンクからナイトサファリの予約ページへアクセスして、貴重な夜の生き物探しを体験してみてください:ナイトサファリツアーはこちら
この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。


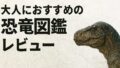
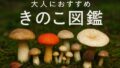
コメント