その名が示す通り、デビルズホール・パプフィッシュはまさに地獄のような環境に生息しています。
アメリカ・ネバダ州の砂漠にある水没した洞窟に閉じ込められたこの魚は、年間を通して摂氏33度前後の水温、乏しい食料資源、そして非常に低い酸素レベルという、ほかの魚のほとんどが即死してしまう環境で生き延びているのです。
さらに、彼らは世界でも最も近親交配が進んだ脊椎動物のひとつとされており、幅約3.5メートル・長さ約22メートルの狭い洞窟に、わずか数百匹しか生息していません。
その遺伝的多様性は極めて低く、4から5世代にわたる兄弟姉妹間の交配と同等とされるほどです。
このように、デビルズホール・パプフィッシュは極限の環境の中で生き延びている、きわめて珍しい魚なのです。
本記事はこの世界で最も近親交配が進んだ魚、デビルズホール・パプフィッシュの驚くべき生態に迫ります。
この記事の要約
- デビルズホール・パプフィッシュは、アメリカ・ネバダ州の砂漠地下にある摂氏33度、低酸素(2〜3ppm)の洞窟水域にのみ生息。世界でもっとも近親交配が進んだ脊椎動物で、全個体が幅3.5m・長さ22mほどの狭い洞窟内に閉じ込められている。
- 酸素が極端に少ない環境で「逆嫌気性(パラドキシカル・アナエロビズム)」という一時的に呼吸を止める行動をとり生き延びる。
- 1960年代から保護活動が続き、地下水使用の制限や人工繁殖施設の建設などが行われてきた。2024年に個体数が回復傾向を見せたが、地震で再び急減。今後は気候変動による水温上昇が最大の脅威とされている。
デビルズホールとは

デビルズホールはアメリカ・ネバダ州の砂漠にある小さな石灰岩の洞窟で、地下深くの空間に、地熱で温められた地下水がたまった池が広がっています。
洞窟の表面積はおよそ長さ22メートル、幅3.5メートルですが、周辺地域の地下水系とつながっており、深さは少なくとも130メートルに達します。
水温は年間を通して約33度と高く、まるで温泉のような状態になっています。
しかも、周囲は世界でも最も暑い砂漠のひとつであるデスバレーに近く、外気の影響も加わって、冷えることがほとんどないのです。
また、水温が高いと酸素は水に溶けにくくなるうえ、デビルズホールの水はほぼ静止状態で、水草も少ないから酸素を供給する要素がほとんどありません。
その結果、酸素濃度は2から3ppmほどしかなく、これは普通の魚なら即死レベルの低さです。
デビルズホール・パプフィッシュの特徴

このデビルズホールにのみ生息している、世界で唯一の魚がデビルズホール・パプフィッシュです。
デビルズホール・パプフィッシュは酸素の非常に少ない環境に適応する中で、「逆嫌気性(パラドキシカル・アナエロビズム)」と呼ばれる行動を身につけました。
この状態では、魚は仮死状態のようになり、最大で2時間も酸素を呼吸せずに過ごすことができます。
これにより、低酸素環境でも活動を維持し、限られた資源の中で生き延びることが可能となっているのです。
デビルズホール・パプフィッシュの体長は最大で約3センチと小型で、色彩は年齢や性別によって異なり、成魚のオスは明るいメタリックブルーに輝き、メスや幼魚は黄色みを帯びています。
また、この種の大きな特徴として、腹びれが欠如している点が挙げられます。
デビルズホール・パプフィッシュは年間を通じて繁殖を行いますが、ピークは2月中旬から5月中旬にかけてです。
ただ、メスの産卵能力は低く、1シーズンあたり平均で成熟卵は4~5個程度しか生産されません。そして、1回の産卵で通常1個の卵しか産まないと考えられています。
さらに、低い産卵数に加えて卵の孵化率も低く、幼魚の生存率も低いため、個体群の増加は非常に限られています。
世界最小の生息地

デビルズホール自体は深さ130メートル以上ありますが、パプフィッシュが生息しているのは上層のわずか24メートルほどの範囲に限られており、さらに個体数が最も多いのは水深15メートルより上の浅い層です。
そのため、この洞窟は脊椎動物の全個体群の生息地としては世界最小であるともいわれています。
これは、洞窟の一端に水深約30センチの小さな岩棚があり、そこがデビルズホール・パプフィッシュにとって限られた餌場であり、産卵場所となっているためです。
研究によれば、この岩棚の藻類の量は日照や栄養塩の供給によって変動します。そして、藻類が多いとそこに住む個体の餌も豊富になるため、年間の個体数も増えるのです。
また、洞窟がアナホリフクロウのねぐらや繁殖地として使われると、フクロウのペリットが水中に落ちることがあります。
ペリットとは鳥が食べたもののうち、消化できなかった骨や羽毛、毛などを丸めて吐き出したもので、栄養分が豊富なため藻類の成長を助ける栄養源となります。
食性と天敵

そのほか、デビルズホールパプフィッシュは限られた洞窟環境の中で、ほぼすべての入手可能な食物を摂取します。
その食性は季節によって変化し、藻類のほかに甲虫やカタツムリといった小型の無脊椎動物、淡水性の甲殻類など、多様な食物を食べています。
生息地が非常に狭く孤立しているため、利用できる食物資源を効率よく摂取することが生存の鍵となっているのです。
デビルズホール・パプフィッシュの天敵として知られているのは、捕食性のゲンゴロウの一種であるNeoclypeodytes cinctellus(ネオクリペオディテス・チンクテルス)です。
この昆虫はパプフィッシュの卵や幼魚を捕食します。また、パプフィッシュと同じようにいくつかの無脊椎動物も捕食するため、単なる捕食者であるだけでなく、餌資源をめぐる競争相手でもあります。
この昆虫は比較的新しくこの生態系に加わった存在で、デビルズホールで初めて観察されたのは1999年か2000年頃です。
限られた生息環境の中で、この捕食者と餌の競合はパプフィッシュの個体数や生存に大きな影響を与えています。
分類と起源

この魚はカダヤシの仲間で、1930年に初めて学術的に記載されました。
近縁種にはアマルゴサ・パプフィッシュやデスバレー・パプフィッシュがあり、いずれもモハーヴェ砂漠やデスバレーのような過酷な砂漠環境の中で、泉や川、湖など限られた水域に生息しながら生き抜いています。
デビルズホールパプフィッシュがどのようにデビルズホールに棲むようになったのかははっきりしていません。
ただ、いくつかの仮説があり、地下水を通って到達した可能性や、一時的な水路や湿地を移動してきた可能性が考えられています。
また、ネイティブ・アメリカンがパプフィッシュ類を食用として利用していたことから、意図的か偶然かにかかわらず、彼らによってデビルズホールに持ち込まれた可能性も指摘されています。
遺伝学の研究によると、この種がアマルゴサ・パプフィッシュとの共通祖先から分かれたのは、数百年から数千年前と推定するものもあれば、最大で6万年前とするものもあります。
脅威と保全の歴史

デビルズホール・パプフィッシュは世界でも最も近親交配が進んだ脊椎動物のひとつであり、生息地の破壊や環境の変化、新たな病気の脅威など、さまざまな外的な圧力にさらされています。
この種は、わずか一か所の環境にしか生息していないため、非常に外的な影響に弱い魚です。
鉄砲水や地震などの自然災害によって容易に乱されることがあり、人類はこの小さな魚を守るために長年にわたって様々な努力を続けてきました。
1940年代後半にこの種の保護運動が始まり、1952年にデビルズホールがナショナルモニュメント(現国立公園)の一部に指定されています。
しかし、1967年頃から始まった周辺農場による地下水の大規模な汲み上げにより、デビルズホールの水位が低下しました。
これにより、魚が唯一産卵・採餌する浅瀬が露出し始めたのです。
そして、1967年に絶滅危惧種に公式に指定されると、保護派と開発業者との間で激しい法廷闘争が展開されます。
保全活動は費用がかかり、地元の農家は水の利用権を制限されることに不満を持っていました。このことから、「パプフィッシュを殺せ」という声と、「パプフィッシュを守れ」という声が対立する論争となっていたのです。
1970年には人工の棚が設置されましたが、デビルズホール・パプフィッシュはこれを利用しませんでした。
結局、1976年の合衆国最高裁判決により、パプフィッシュの生存に必要な最低水位を維持するために地下水利用が制限されることとなり、個体数は一旦回復しました。
継続する危機と対策

しかし、地下水問題が解決した後も、危機は終わりませんでした。
1970年代から1996年まで平均324匹で推移していた個体数は、再び減少し始め、2005年以降は200匹を下回る低迷期に入ります。
この減少の理由は不明ですが、近親交配の影響、食料源の変化、堆積物の変動などが仮説として挙げられました。
この頃、自然災害や人為的な被害も顕在化します。大規模な地震が起こるたびに立ち波が発生し、浅瀬に付着した藻類や卵を洗い流して生息環境を破壊したのです。
また、2004年には鉄砲水で観測機器が流され、約80匹が死亡、さらに2016年には侵入者が保護区域で機器を破壊し、浅瀬を踏みにじるという悪質な事件も発生しました。
これらの脅威を受け、有刺鉄線の追加や、カメラ・センサーの増設といった対策が強化されました。
域外保全の成功と最新の状況

このような野生下での危機に備え、1960年代から水族館や人工池への移植による域外保全が試みられてきましたが、ほとんどが失敗に終わっています。
しかし、2010年代初頭に約450万ドルを投じて建設された「アッシュメドウズ魚類保全施設」に、デビルズホールの環境を忠実に再現した巨大な水槽が完成しました。
ここでは水温や酸素量を調整し、魚のストレスを軽減する工夫が凝らされ、安定した人工繁殖個体群の維持に成功しました。
この成功と、2023年のハリケーンによる藻類増加などの要因もあり、個体数は回復傾向に転じます。2024年春には191匹と25年ぶりの高水準を記録しました。
しかし、同年末から2025年初頭にかけての2度の地震による破壊で、その数は翌春にわずか38匹に急減しました。
これを受け、初めて人工繁殖個体の19匹が野生に放たれるという緊急措置がとられています。
これまでのさまざまな脅威に加え、将来的には気候変動による気温の上昇も大きな脅威になると予想されています。
水温が上昇すると、繁殖や成長に適した期間が短くなり、次世代の個体が安定して育たなくなるおそれがあるのです。
デビルズホール・パプフィッシュの歴史は、人類の絶え間ない保全努力と、環境および遺伝的な脆弱性との闘いの記録といえるでしょう。


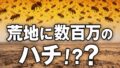

コメント