2017年8月19日、アメリカ・ワシントン州のピュージェット湾北部、サイプレス島沖で、約30万5,000匹のタイセイヨウサケを飼育していたいけすが崩壊し、大量のサケが海に逃げ出すという前代未聞の事故が発生しました。
このサケは北米東部が原産で、ピュージェット湾のような北西部の海域には本来生息していない外来種です。
本記事ではなぜこのような事故が起きたのか、そして、逃げ出したサケが地域の生態系にとってどのような脅威となっているのかについて、その背景を説明しています。
養殖いけす崩壊の背景

このいけすはワシントン州にあるクックアクアカルチャーパシフィック社の9つの養殖施設のうちのひとつでした。
同社はすでにメイン州やカナダのニューブランズウィック州で最大手のサーモン養殖業者であり、さらにチリやスコットランドにも進出していました。
こうして太平洋岸北西部でも大規模な事業拡大を進めていたのです。
クック社は積極的な拡大路線によって、世界最大の民間サーモン養殖企業にまで成長しましたが、その勢いはまもなく大きな壁に直面することになります。
崩壊した養殖いけすは「ネットペン」と呼ばれる方式のものでした。
ネットペン養殖とは海や湖などの水域に設置した大きな網のケージで魚を育てる養殖方法です。
このケージは海面に浮かぶ浮き枠に網を吊り下げた構造になっており、全体がロープや鎖で海底のアンカーに固定されています。
これにより、潮の流れや風によって流されることなく、一定の場所にとどまります。
養殖場の崩壊後、8月21日にはちょうど皆既日食が起きていました。
そのため、クック社は崩壊の原因は日食の前後に発生した高潮や強い海流によるものだと主張しました。
しかし本来、養殖用のいけすは設置された場所の潮流・風・波などの自然条件に耐えられるように設計・管理されているものです。
実際、このいけすは事故前の7年間、問題なく稼働しており、それ以前も近隣の海域で9年間使用されていました。
また、事故当時の環境条件は特別に厳しいものではなく、通常の範囲内であったことが、のちに科学的に証明されています。
それにもかかわらずいけすが崩壊した背景には、クック社による網の清掃不足をはじめとする管理上の問題がありました。
まず、衛生管理が不十分だったことで、ムール貝などの海洋生物が網に大量に付着していました。
さらに、網の清掃装置が故障していたこともあり、状況は一層悪化していたのです。
このように網に生物が付着したことで、潮流を受けた際の水の抵抗が増加し、いけすを固定していた係留システムの耐久力を超えてしまいました。
その結果、7月24日から25日にはアンカーの引きずりや係留ロープの破損が起き、いけすが大きく移動し、8月19日には構造フレームの損傷も重なり、最終的にいけすが崩壊したのです。
こうして、大量のサケが海へ流出しました。
クック社の対応と不十分な報告

8月19日にいけすが崩壊した後、クック社は多額の資源を投入して施設の復旧を試みましたが、最終的には失敗に終わりました。
その後、崩れた構造物の安定化や死んだ魚の回収、いけすの撤去作業が進められ、9月24日までに水面上の部分は撤去されました。
しかし、クック社が「海底の残骸はすべて除去した」と報告したにもかかわらず、10月27日に天然資源局(DNR)が行った調査では、多くの残骸が依然として残っていることが確認されました。
そのため、DNRは追加の清掃を命じ、作業は翌年1月まで続けられることになりました。
また、逃げ出したサケの数についても、クック社の報告には大きな誤差がありました。
事故前、いけすには約30万5,000匹のタイセイヨウサケが養殖されていましたが、クック社は崩壊後に14万5,000匹を回収したと報告しています。
ところが、調査委員会の分析によると、実際に回収されたのはわずか4万2,000から6万2,000匹程度で、クック社の報告の約43%にすぎませんでした。
この分析から、実際には約24万3,000から26万3,000匹が海に逃げ出したと推定され、クック社が報告していた約16万匹という数字を大きく上回っていました。
さらに問題だったのは、クック社の情報提供の不十分さです。
州政府機関は、7月の事故について十分な情報を得られず、適切な対応を取ることができませんでした。
クック社が正確で完全な報告を行わなかったため、州側は事故の深刻さを把握できず、追加の調査も実施されないまま時間が経過してしまったのです。
逃げ出したサケの緊急漁獲活動

クック社は逃げ出した魚によって在来の生態系が脅かされる可能性について、深刻に受け止めていない姿勢を示していました。
同社の代表は「サケはアザラシの餌となり、漁師たちはその状況を楽しむことができる」と発言していたのです。
一方、8月の大規模ないけす崩壊事故を受けて、ワシントン州の複数の政府機関が連携し、対応に乗り出しました。
主要な3つの機関は統合事故指令本部を設置し、現場の安全確保やクック社による安定化・回収作業の監視、州および連邦機関との連携、逃げ出した魚の数や健康状態の記録、さらに一般市民や他の政府機関への情報提供など、多岐にわたる対応を行いました。
ワシントン州魚類野生生物局は、漁業権が条約によって保障されている先住民族(条約部族)やカナダ政府と協力し、逃げ出したタイセイヨウサケの捕獲を目的とした緊急漁獲活動を開始しました。
これは、主に逃げた魚が河川に入り込み、在来のサケと交雑するのを防ぐための措置でした。
タイセイヨウサケはサケ科に属する魚類の一種で、大西洋北部沿岸とそこに流入する河川に広く分布しており、ヨーロッパ側では北部沿岸に、北アメリカ側ではアメリカとカナダの東海岸沿岸に生息しています。
成長が早く安定して大きく育てやすいこと、餌や飼育環境によって味や脂質を調整できること、そして天然ものに比べて寄生虫の心配が少ないことなどからタイセイヨウサケの養殖は世界的に広く行われており、特にノルウェーやスコットランド、カナダ、チリなどで商業規模の生産が盛んです。
現在、市場に流通しているタイセイヨウサケの大半は養殖ものであり、回転寿司などでサーモンと表示される魚の多くは本種か、ニジマスを海で養殖したトラウトサーモンです。
逃げ出したこのタイセイヨウサケは、ワシントン州に生息する在来のサケと餌や産卵場所をめぐって競合する可能性があります。
これにより、在来種の生存率が低下し、個体群の維持に支障をきたす恐れがあります。
また、在来のサケとは属が異なるため交配の可能性は低いものの、繁殖行動による生態的混乱や、遺伝的多様性の損失につながる懸念も指摘されています。
さらには養殖由来の病気や寄生虫を野生魚に伝播させるリスク、排泄物や食べ残しによる水質汚染など、地域の生態系にさまざまな影響を与える懸念もあります。
逃げ出したサケの捕獲には、一般の釣り人や商業漁師も参加を許可され、多くの住民や先住民の部族が協力して漁を行いました。
こうして、約5万7,000匹は捕獲されましたが、依然として18万6,000から20万6,000匹のサケが行方不明のままとされています。
この影響はサケの世代を超えて長く残ると考えられています。
事故の数週間後には、逃げ出したタイセイヨウサケが南はタコマ付近、北はカナダ・ブリティッシュコロンビア州のバンクーバー島付近まで確認されました。
さらに、複数の場所で小型の在来サケを飲み込んだタイセイヨウサケも捕獲されています。
この大量脱走はちょうどサケの産卵期と重なっていたのです。
法改正とアメリカの対応

2017年のいけす崩壊事故の後、ワシントン州議会は沿岸の養殖いけす施設によるタイセイヨウサケの飼育を段階的に廃止する法律を制定しました。
これにより、州内での外来サケの海上飼育は事実上禁止されることとなりました。
この法改正は、事故によって逃げ出したサケが在来種と交雑するリスクや病気の拡散、環境への影響を引き起こす可能性があることを重く見た結果です。
また、州政府は養殖業者とのリース契約の見直しやキャンセルも進め、より厳格な管理体制を整える方向へと舵を切りました。
現在では、陸上養殖など、より閉鎖的で環境への影響が少ない方法への移行が検討されており、海洋環境での外来種養殖は大きく制限される流れとなっています。
クック社はワシントン州から332,000ドルの罰金を科され、過失と認定されました。
また、タイセイヨウサケの商業養殖を禁止する法律に伴い、2025年までに全てのネットペン養殖を終了させる方針を示しました。
これにより、クック社はワシントン州内の養殖場の営業権を失い、2023年春にはこれらの施設が撤去されています。
たった一度の事故が、生態系にどれほど大きな影響を与えるのか。
その教訓は、人間が自然とどう向き合うかを静かに問いかけています。
関連記事:大人向け!魚の世界を深く知るおすすめ図鑑11選 | ジオチャン
日本でも深刻化する外来種問題
このような外来種による生態系への脅威は、アメリカだけの問題ではありません。
日本でも、アライグマ、ヌートリア、オオクチバス(ブラックバス)、アメリカザリガニなど、数多くの外来生物が在来の生態系に深刻な影響を及ぼしています。
外来種問題についてより深く知りたい方には、自然環境研究センター編『最新 日本の外来生物』(平凡社、2019年)をおすすめします。
この本では、日本に生息するすべての侵略的外来種を592ページにわたってカラー写真付きで詳しく紹介しており、在来種との見分け方や防除の方針、海外の事例なども掲載されています。
外来種問題を正しく理解することは身近な自然を守る第一歩となるでしょう。
この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。


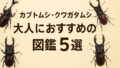

コメント